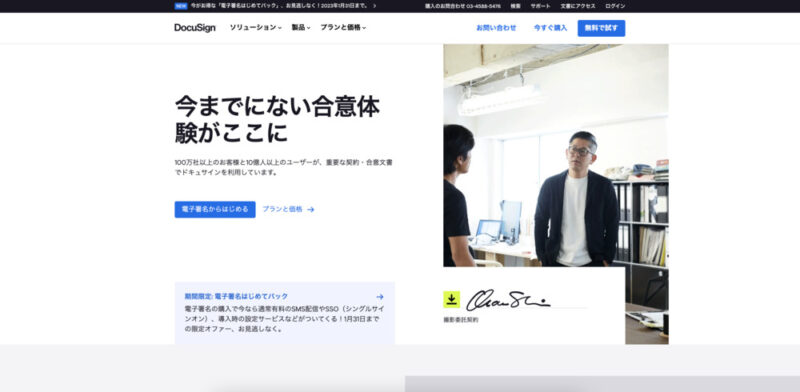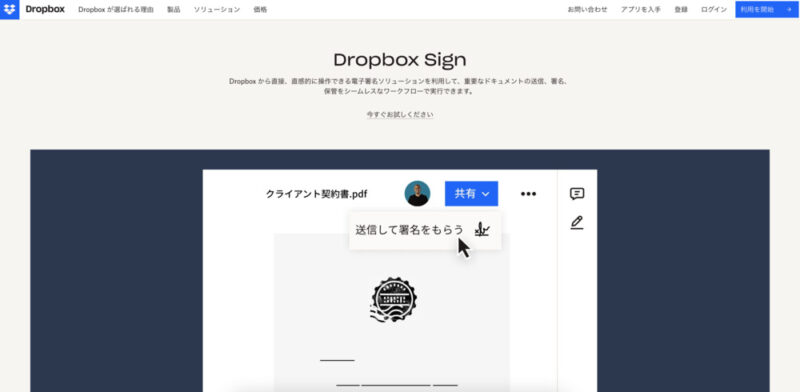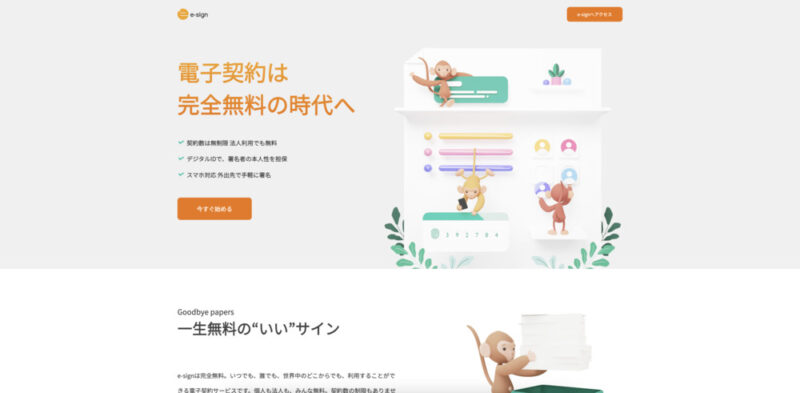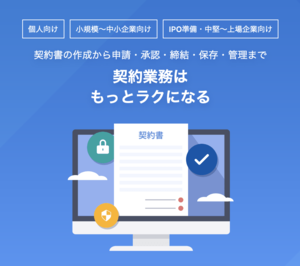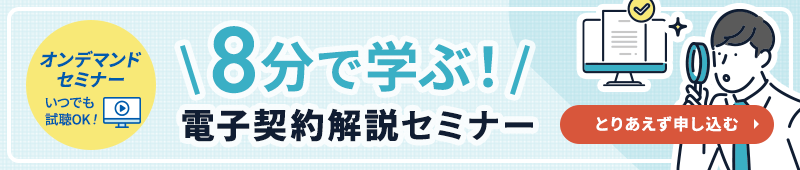最終更新日:2024年4月25日

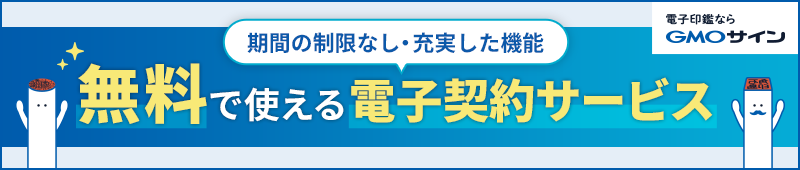
GMOサインは導入企業数“No.1”の電子契約サービスです。個人事業主から大企業まで幅広く導入されています。また、業種を問わずさまざまな場面で活用されています。
無料プランは毎月5件送信することができ、さらに⽂書テンプレートやアドレス帳機能などの豊富な機能を標準搭載しています。しかも期間の制限がないので永年無料で利用可能です。
有料プランは月額9,680円 (税込) のシンプルワンプランでわかりやすく、多彩な便利機能を搭載しながら、送信料は110円 (税込) と業界最安値クラスです。他社サービスと比較しても圧倒的なコスパの良さです。
デジタル経済の発展に伴い、年々需要の高まりつつある「電子契約」。契約業務効率化やコスト削減を目的にさまざまな企業で導入されています。また、官公庁や各地方自治体でも電子契約の導入が進んでいます。
このページでは、電子契約比較ドットコム編集部が厳選したおすすめの電子契約サービスを紹介するとともに、失敗しない選び方やメリット・デメリットなどを解説するので、ぜひ参考にしてください。
『無料』で使える電子契約サービス比較表【2024年4月最新版】
 電子印鑑GMOサイン | 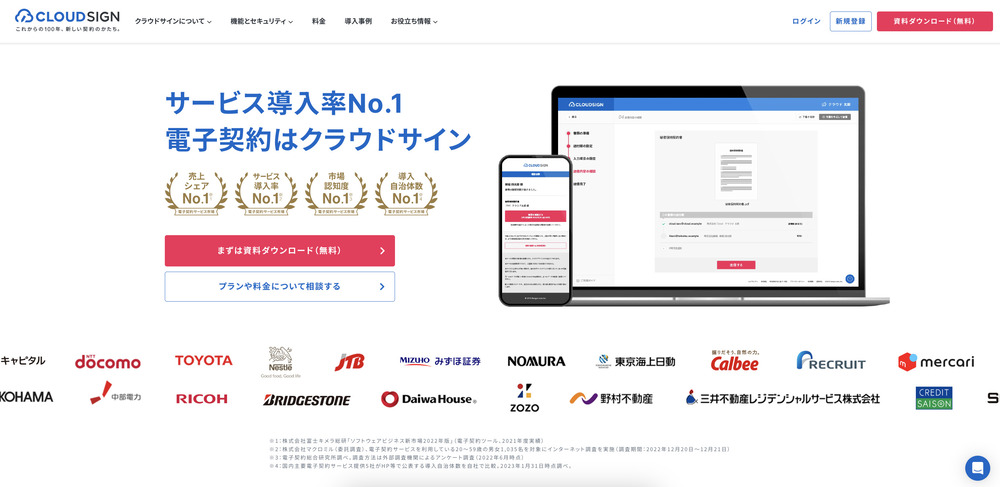 クラウドサイン |  freeeサイン | 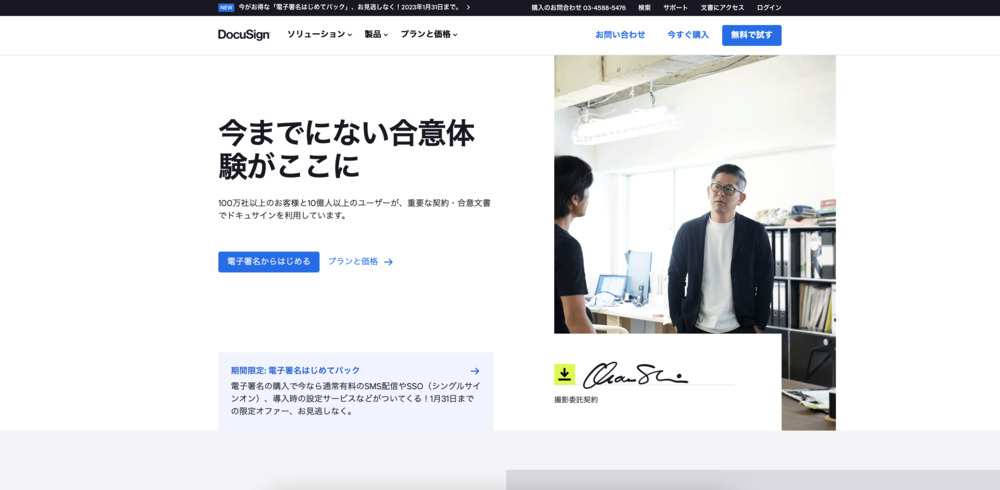 ドキュサイン |  Adobe Acrobat Sign | 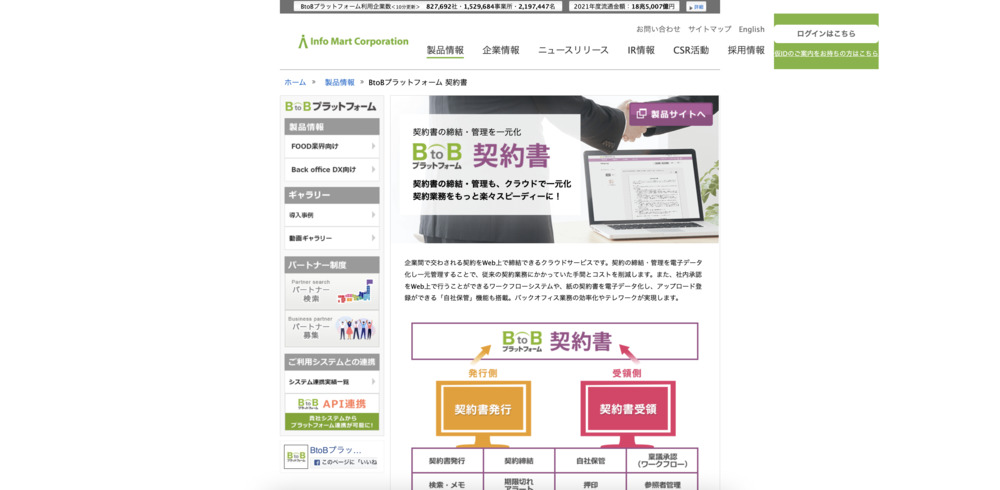 BtoBプラットフォーム 契約書 |  WAN-Sign |  みんなの電子署名 |  DX-Sign |  FAST SIGN |  契約大臣 |  リーテックスデジタル契約 | 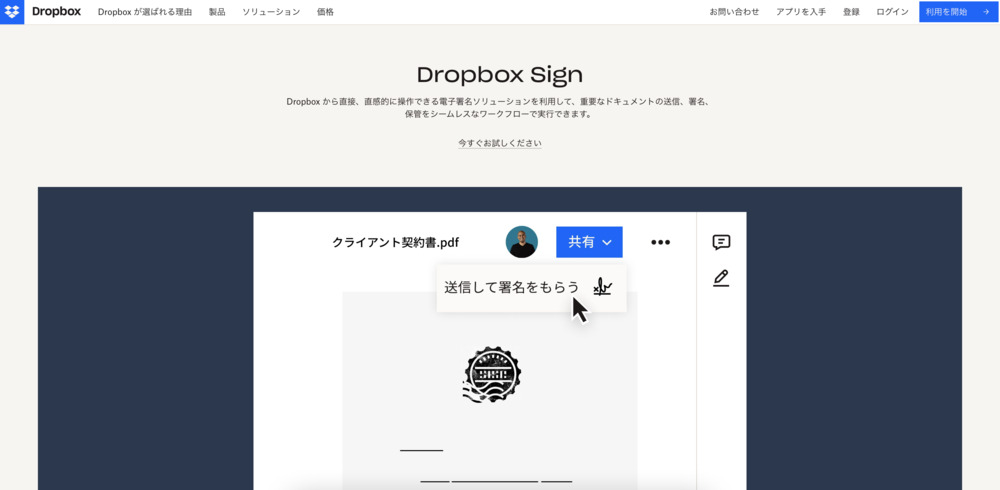 Dropbox Sign |  サインタイム |  セコムWebサイン |  Great Sign |  CoffeeSign |  eformsign |  DottedSign |  e-sign | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 | 無 | 有/30⽇間 ビジネスプロと同等の機能が期間限定で利⽤可能 | 有/7⽇間 Acrobat Proプランの無料お試し | 無 | 無 | 無 1年以上経過した文書に対して料金が発生する | 無 | 無 | 無 | 無 | 有/30⽇間 Standardプランの無料トライアルを想定 | 無 | 有/30⽇間 | 無 | 無 | 有/30日間 | 無 | 2023年6月30日をもってサービス終了 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無制限 | 電⼦証明書発⾏が必要 8,800円/年 | 無制限 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 不明 | 1 | 不明 | 無制限 | 不明 | |
| 送信数/月 | 5件 | 3件 | 1通 | 100件/年 | 無制限 | 5件 保管は3件まで | 契約締結3件 送信のみの場合10件 | 無制限 | 5件 | 10件 送信のみで契約締結は不可 | 1件 | 0件 受け取りのみ | 無制限 送信のみ | 合計25通まで無料 | 不明 | 10件 | 5件 | 100件 | 3件 | ||
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||
| 手書きサイン | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||
| 印影登録 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||
| 認定タイムスタンプ | 不明 | 電⼦署名:利⽤不可 タイムスタンプ:有り | オプション対応 | 不明 | |||||||||||||||||
| 契約締結証明書 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
| 署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
| アクセスコード認証 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
| ⽂書テンプレート登録 | PDFのみ | 1件のみ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | |||||||||||||
| アドレス帳 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||
| 下書き保存 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||
| 契約更新の通知 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
| フォルダ作成 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | ログイン時の二要素認証のみ可能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ||
| 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | ||||||||
| 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 |
『無料』で使える電子契約サービス比較表のダウンロード
編集部厳選!『無料』で使える電子契約サービス20選
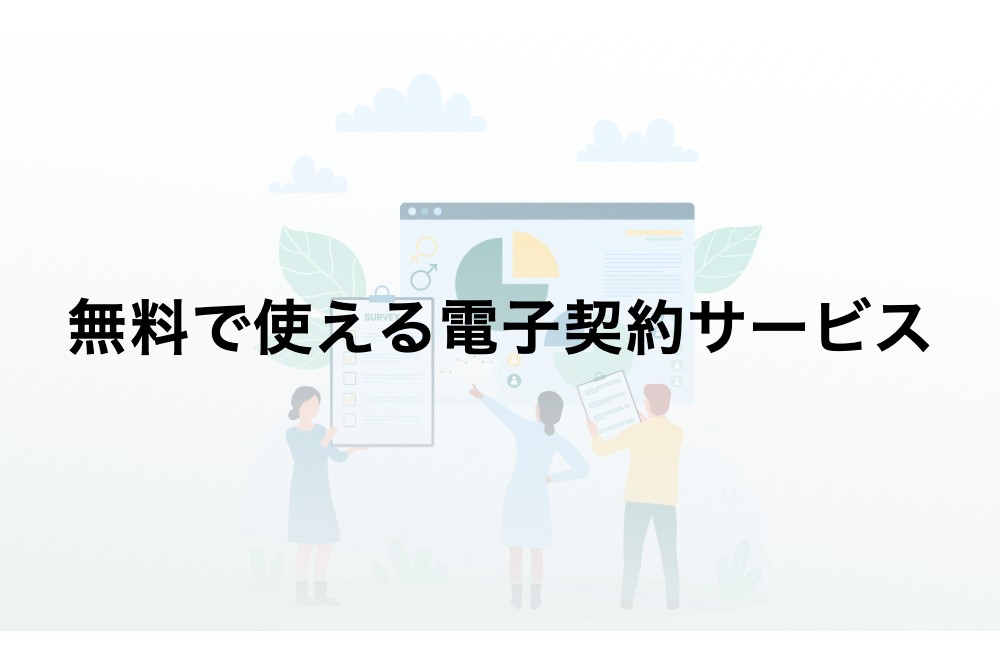
電子契約比較ドットコム編集部が厳選した「“無料”で使えるおすすめの電子契約サービス」を紹介します。いずれも無料で利用できますが、各サービスによって送信数の上限や機能などが大きく異なりますので、それぞれの特徴や違いを比較し、最も自社に合った電子契約サービスを選びましょう。
\ボタンを押すと該当箇所にジャンプします/
無料で使える電子契約サービス一覧
電子契約サービスを調べてみても、実際に使ってみなければ具体的な判断はできないでしょう。大手の電子契約サービスの中には一定期間の無料利用や、一定枚数までの試用が可能なものがあるため、一度試してみてはいかがでしょうか。
電子契約自体が初めての方は、無料期間でその利便性を体験してみるのもよいでしょう。納得のいくサービスを見つけるため、無料期間を積極的に活用することをおすすめします。
GMOサイン
引用元:GMOサイン
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | ||
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |

GMOサインは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が運営する電子契約サービスです。300万社(※2023年11月時点)以上の企業が導入しており、個人事業主から大企業まで幅広く利用されています。
GMOサインの無料プラン(お試しフリープラン)では、毎月5件送信することができ、⽂書テンプレートやアドレス帳機能などの各種機能を搭載しているため、電子契約を無料で試すのにぴったりです。さらに、“利用期間の定めなし”で永年無料で使い続けることができるのも嬉しいポイントです。また、電⼦帳簿保存法にも対応しています。
有料プランにアップグレードすれば、毎月の送信数や登録ユーザー数が無制限となり、本人性が高い実印タイプでの署名も可能になります。送信数や登録ユーザー数の上限を気にすることなく、より幅広いシーンで活用できるようになります。
やらせ一切なし!GMOサインのリアルな評判・口コミを見る
クラウドサイン
引用元:クラウドサイン
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 3件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | オプション対応 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとクラウドサインの機能比較
 GMOサイン | 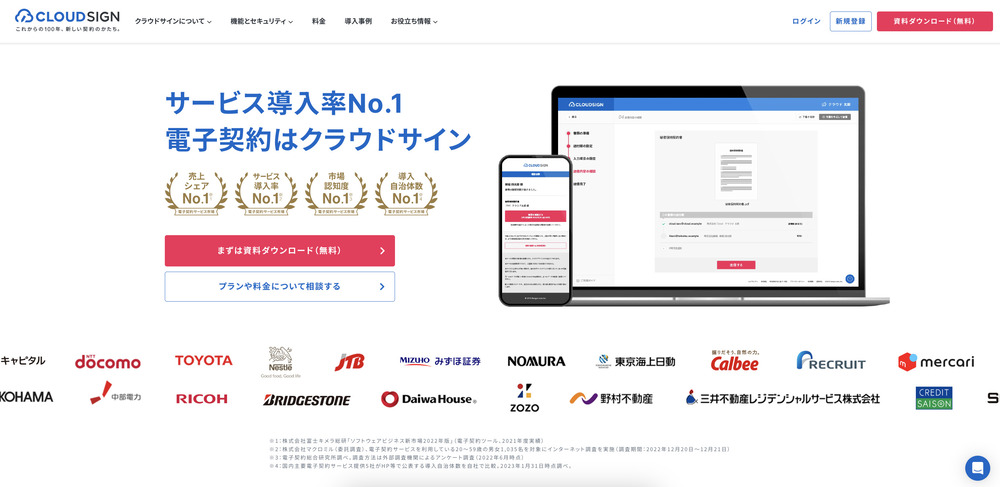 クラウドサイン | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 3件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | オプション対応 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | |||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | |||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
弁護士ドットコム株式会社の運営するクラウドサインは、250万社(※2023年11月時点)以上の導入実績を誇り、国内シェアNo1の電子契約サービスです。国内での知名度が非常に高く、業界業種問わずさまざまな企業で活用されています。
クラウドサインの無料プランでは、毎月3件まで送信可能です。2023年7月以前は5件まで送信可能でしたが、送信件数の上限変更に伴い、3件までとなりました。
その他の機能についてはこれまで通り利用することが可能なので、立会人型の電子署名(契約印タイプ)とタイムスタンプも引き続き無料で利用できます。
クラウドサインの評判・口コミを見る
freeeサイン
引用元:freeeサイン
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 1通 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | PDFのみ | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | ログイン時の二要素認証のみ可み |
GMOサインとfreeeサインの機能比較
 GMOサイン |  freeeサイン | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 1通 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | |||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | ||
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | PDFのみ | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | |||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | ログイン時の二要素認証のみ可み |
freeeサイン(旧称 NINJA SIGN)は、freeeサイン株式会社が運営する電子契約サービスです。契約文書の作成から契約締結、文書管理まで煩雑なプロセスをオンラインで完結可能です。弁護士が監修しているため、信頼性が高く、安心して利用することができます。テレワークでの利用にも最適です。
freeeサインでは利用目的に応じたプランが用意されているので、企業規模によって使い分けることができます。必要な機能や送信数などに応じて自社に合ったプランを選べるのが嬉しいポイントです。無料期間については非公開なので問い合わせが必要です。
ドキュサイン
引用元:ドキュサイン
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 有/30⽇間 ビジネスプロと同等の機能が期間限定で利⽤可能 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 100件/年 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | ||
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとドキュサインの機能比較
 GMOサイン | 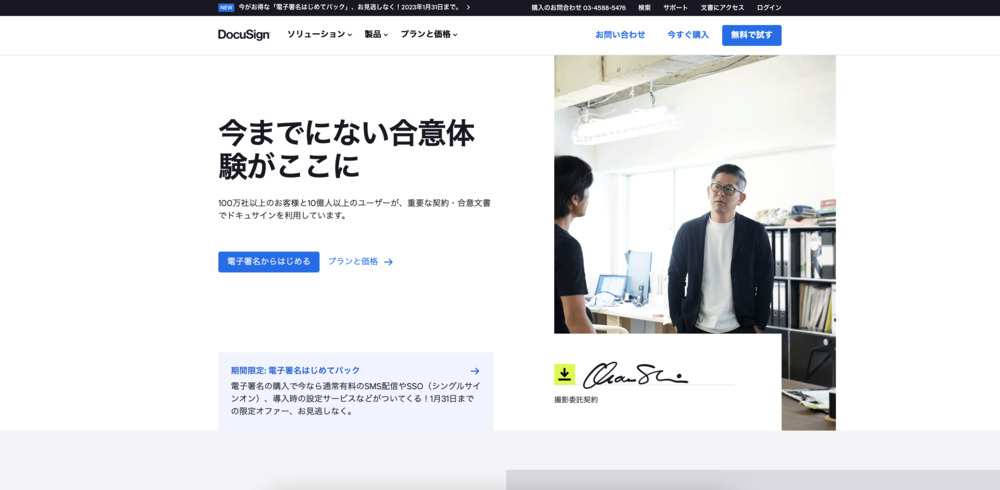 ドキュサイン | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 有/30⽇間 ビジネスプロと同等の機能が 期間限定で利⽤可能 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 100件/年 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | |||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | ||
| 署名順設定(順列/並列) | |||
| アクセスコード認証 | |||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | |||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | |||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
ドキュサインは、180以上の国・地域で利用されている電子契約サービスです。業界最多の44言語で署名することができます。また、送信可能な言語数も14言語と非常に多いです。
無料プランの用意はありませんが、30日間無料で試すことができるので手軽に使用感を確認できます。クレジットカードを登録する必要がなく、メールアドレスのみで利用可能なのも嬉しいポイントです。
機能も充実していて、堅牢なセキュリティで安心して利用することができます。直感的に操作できる仕様となっており、PCだけでなく、スマートフォンやタブレット端末でも使いやすいです。
Adobe Acrobat Sign
引用元:Adobe Acrobat Sign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 有/7⽇間 Acrobat Proプランの無料お試し |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 無制限 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとAdobe Acrobat Signの機能比較
 GMOサイン |  Adobe Acrobat Sign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 有/7⽇間 Acrobat Proプランの無料お試し |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 無制限 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | |||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
Adobe Acrobat Signは、様々なクリエイティブツールでお馴染みのAdobe(アドビ)が運営する電子契約サービスです。PDFの作成、編集、共同作業、署名、共有などを簡単に行うことができ、電子署名との互換性も抜群です。また、日本国内においても法的有効性が認められているので、安心して利用することができます。
個人版限定ですが、Acrobat Proを7日間無料で体験することができ、ほぼすべての機能を手軽に試せます。
BtoBプラットフォーム 契約書
引用元:BtoBプラットフォーム 契約書
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 無制限 |
| 送信数/月 | 5件 保管は3件まで | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | |
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとBtoBプラットフォーム 契約書の機能比較
 GMOサイン | 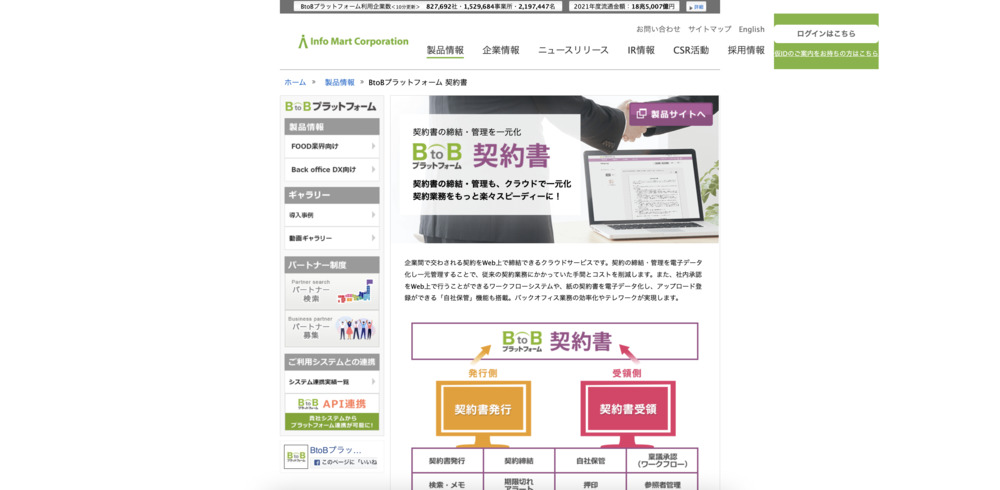 BtoBプラットフォーム 契約書 | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 無制限 |
| 送信数/月 | 5件 | 5件 保管は3件まで | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | |||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | ||
| アクセスコード認証 | |||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | |||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | |||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
BtoBプラットフォーム 契約書は、株式会社インフォマートが運営している電子契約サービスです。安全な電子契約サービスの提供をモットーに運営しており、利用企業数は100万社以上にも上ります。
会社の規模や業種の制限がなく、ほとんどの企業が利用できるスタイルで、導入のハードルがとても低く設定されているのが特徴です。また、機密性や信用性の確保に力を入れており、最新のブロックチェーン技術を使用した、安全性の高いサービスとなっています。
BtoBプラットフォーム 契約書には有料プランとフリープランが用意されています。フリープランはBtoBプラットフォーム 契約書の機能を試してみたい方向けとなっており、ユーザー数は無制限、電子契約は月に5件まで、そして電子保管は3件までと制限されています。しかし、特に利用期間は決められていないので、この条件でも問題ないのであれば、フリープランで使用し続けることができるようになっています。
まずはフリープランで試してみて、使い勝手が良いと感じたら有料プランに移行するのも良いでしょう。
WAN-Sign
引用元:WAN-Sign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 電⼦証明書発⾏が必要 8,800円/年 |
| 送信数/月 | 契約締結3件 送信のみの場合10件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | ||
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | ||
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとWAN-Signの機能比較
 GMOサイン |  WAN-Sign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 電⼦証明書発⾏が必要 8,800円/年 |
| 送信数/月 | 5件 | 契約締結3件 送信のみの場合10件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | |||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | ||
| 署名順設定(順列/並列) | |||
| アクセスコード認証 | |||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | |||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | |||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | |||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
WAN-Sign(ワンサイン)は、4,000社以上の情報資産を管理してきた株式会社NXワンビシアーカイブズが運営する電子契約サービスです。業界最高水準のセキュリティによって高い安全性を確保しています。また、無料で使える範囲が広いため、導入しやすいことから注目を集めています。
WAN-Signは、署名タイプ別に送信数が異なる(※無料で使える上限数が異なる)ので注意が必要です。なお、当事者型は3件/月まで、立会人型は10件/月まで送ることができます。
WAN-Signの大きな特徴として、API連携が可能なシステムであれば、“どんなサービス”とも外部連携が可能なので、複雑な業務プロセスの改善によって、業務効率の向上が期待できます。
みんなの電子署名
引用元:みんなの電子署名
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 1年以上経過した文書に対して料金が発生する |
| 契約内容 | ユーザー数 | 無制限 |
| 送信数/月 | 無制限 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | |
| 署名順設定(順列/並列) | ||
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとみんなの電子署名の機能比較
 GMOサイン |  みんなの電子署名 | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 1年以上経過した文書に対して 料金が発生する |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 無制限 |
| 送信数/月 | 5件 | 無制限 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | ||
| 署名順設定(順列/並列) | |||
| アクセスコード認証 | |||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | |||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | |||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
みんなの電子署名は、月額固定料金0円、送信料金0円で利用できる電子契約サービスです。また、機能制限なしですべての機能を使うことができます。利用開始から1年間は“完全無料”で利用可能です。ただし、注意が必要なのは、「1年以上経過した文書の保管料金」がかかるという点です。文書を保管し続けるためには、1枚で50文書の保管が可能なチケット(保管チケット)を購入する必要があります。保管したい文書が多ければ多いほど料金が高くなります。
みんなの電子署名は、「電子署名法」「e-文書法(電子文書法)」「電子帳簿保存法」に準拠しています。さらに、通信と保管の両面で最高水準のセキュリティを備えているので、安心して利用できます。また、署名は10年にわたって有効なのも嬉しいポイントです。
DX-Sign
引用元:DX-Sign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとDX-Signの機能比較
 GMOサイン |  DX-Sign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | |||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
DX-Signは、株式会社クロスベイターが運営する電子契約サービスです。料金プランについては、無料お試しで使用感を確かめられるものから、電子契約に必要な基本機能が使えるプラン(ノーマル)や、更に機能を拡張したプラン(エンタープライズ)と3つ展開されており、必要な機能に応じて幅広く対応できるラインナップになっています。
無料のプランでは、月5件まで送信および電子署名が無料で使えます。基本機能が使えるノーマルプランも一定期間、無料でお試しできるキャンペーンが設けられています。システム導入に関しては、基本操作の解説動画から設定のサポート、個別のオンラインコンサルティング等、サポート面も充実しており、導入はメール認証でスムーズに行えます。
セキュリティ面では、顧問弁護士監修の元、万全の態勢を整えています。保存ファイルをSSL/TLSで暗号化し保存、不正なアクセスからの保護、保管データの自動バックアップ等、万が一への対策も万全です。
FAST SIGN
引用元:FAST SIGN
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 10件 送信のみで契約締結は不可 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | 不明 | |
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | 1件のみ | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとFAST SIGNの機能比較
 GMOサイン |  FAST SIGN | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 10件 送信のみで契約締結は不可 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | 不明 | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | 1件のみ | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
FAST SIGNは、株式会社マルジュが運営する電子契約サービスです。このシステムの特徴は、契約書数に応じた料金プランの設定です。月10件までの無料プラン、契約件数(月100件~)に応じた3つの有料プランがあります。また、各プランに対して必要に応じたオプション(タイムスタンプ、ファイル添付、CSV一括送信、書類インポート)を追加することもできます。必要な機能に絞ることができるので、不必要な経費の削減につながります。
また、このシステムはスマホでの利用がしやすい設計になっており、たとえば契約の相手方が個人となるような雇用契約の場合など、対個人を想定した契約でのサービス提供に強みを持っています。加えて、WEB面接ツール(SOKUMEN)と連携することで、対個人の雇用契約に関してスピーディな対応が可能になります。
セキュリティ面については、SSL/TLSでの暗号化、AWSを採用することによる高パフォーマンスなセキュリティ性を持っています。
契約大臣
引用元:契約大臣
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 1件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | 電⼦署名:利⽤不可 タイムスタンプ:有り | |
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインと契約大臣の機能比較
 GMOサイン |  契約大臣 | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 1件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | 電⼦署名:利⽤不可 タイムスタンプ:有り | ||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
契約大臣は、株式会社TeraDoxが運営する電子契約サービスです。このシステムは月の契約件数が多くない企業、もしくは個人に対して最適なサービスになっています。
プランは、無料で使えるものが月1件、有料になると10件~100件まで契約書が送信できる3つのプランが用意されています。送信できる契約書の件数が少なく設定されていることで、低価格での提供を実現しているサービスです。
また、このサービスの特徴として、複数者間での契約を可能にする機能が備わっている点が挙げられます。最大5者間での契約が可能になるので、社内の承認を得るためのシステムとしても使用できます。
機能については、電子契約に必要なものが含まれており、セキュリティ面もファイルの暗号化やバックアップ等、システムを運用する上で不安になる要素はありません。IT導入補助金2023の対象になっているサービスでもあるので、導入にコスト面で補助が受けられる可能性があります。
リーテックスデジタル契約
引用元:リーテックスデジタル契約
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 5 |
| 送信数/月 | 0件 受け取りのみ | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとリーテックスデジタル契約の機能比較
 GMOサイン |  リーテックスデジタル契約 | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 5 |
| 送信数/月 | 5件 | 0件 受け取りのみ | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
リーテックスデジタル契約は、リーテックス株式会社が運営する電子契約サービスです。契約件数による従量課金ではなく、一定の件数ごとの定額制をベースに料金プランが分かれている点が特徴です。また、このサービスの強みは、電子署名法に加えて、電子記録債権法を併用している点にあり、法的安全性の高いサービスとなります。無料のエントリープランは5件、有料のプランになると年間360件(月30件)からのプランとなっています。
セキュリティ面については、サーバーに保存されるのではなく、Google Cloudプラットフォーム上に構築されたサービスであり、クラウドサーバー上に保存されます。クラウドサーバー上に構築されたサービスですが、2要素認証でログインをするため、他者に閲覧される不安もありません。文書は暗号化されて保存されるため、信用性が高いサービスとなっています。
このサービスもIT導入補助金の対象となっているため、有料プランへの切り替えに前向きになれるサービスの1つです。
Dropbox Sign
引用元:Dropbox Sign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 有/30⽇間 Standardプランの無料トライアルを想定 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 無制限 送信のみ | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとDropbox Signの機能比較
 GMOサイン | 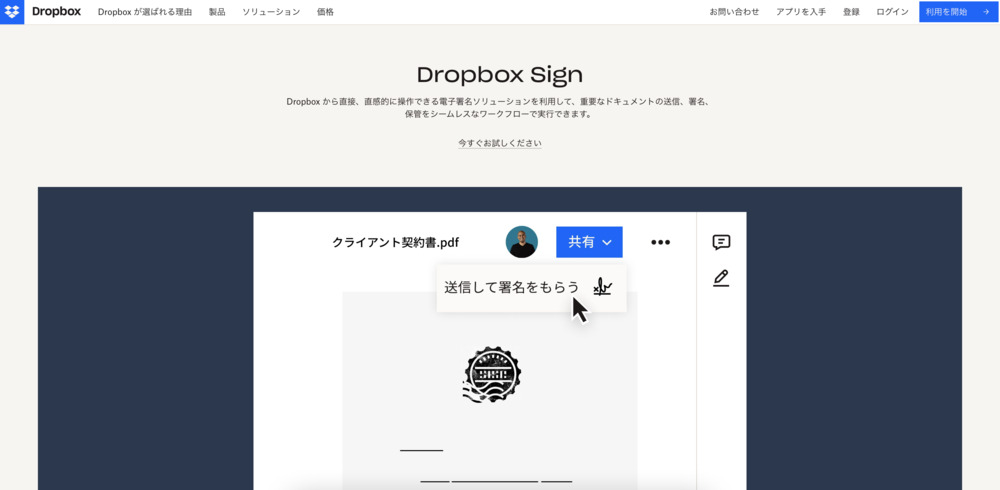 Dropbox Sign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 有/30⽇間 Standardプランの無料トライアルを想定 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 無制限 送信のみ | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | |||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
Dropbox Sign(旧称 HelloSign)は、アメリカのクラウドストレージサービスを展開している会社が運営している電子契約サービスです。用意されているプランは4つあり、それぞれ無料トライアルが実施できます。特徴は、月の契約書件数ではなく、テンプレートの数やインテグレーションの範囲などで料金プランが変わってくる点にあり、他にはないプラン展開となっています。
システムの画面はすっきりしていて、ごちゃごちゃとボタンがある画面が好きではない人に使いやすい設計になっています。保存された文書は、Dropboxが管理するサーバーに保管され、パソコン、スマートフォン、タブレット等のどのデバイスからでもアクセスできる仕様になっています。
また、Dropboxが運営しているソフトのほか、GoogleやMicrosoft、Adobeといった、仕事でよく利用するソフトと連携することもできるため、拡張性の高さが魅力のサービスです。
サインタイム
引用元:サインタイム
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 3 |
| 送信数/月 | 合計25通まで無料 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | ||
| 認定タイムスタンプ | オプション対応 | |
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとサインタイムの機能比較
 GMOサイン |  サインタイム | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 3 |
| 送信数/月 | 5件 | 合計25通まで無料 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | |||
| 認定タイムスタンプ | オプション対応 | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
サインタイム(SignTime)では、ドラッグアンドドロップなど基礎的な操作だけで契約書に署名できるので、操作が他の電子契約サービスと比べて非常に簡単な点が魅力です。またSNSやファイル添付、ハンコ機能などさまざまな機能を備えていますので、応用が利きやすいです。ハンコ機能には文字制限がなく、縦横や改行を入れられるので、個人名だけでなく会社や店舗のハンコも作成できます。さらに1,078円(税込)という手軽な料金でサービスを利用できる点も大きな特徴です。無料で使える30日間お試しプランもあるので、気軽に試せます。
取引先はサインタイムのアカウントを作成する必要がないので、相手に負担をかけさせないメリットもあります。電子契約サービスではセキュリティが重要ですが、サインタイムは締結された契約書をロックして改ざんできないようにする機能があるので安心してお使いいただけます。
セコムWebサイン
引用元:セコムWebサイン
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 有/30⽇間 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 不明 |
| 送信数/月 | 不明 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとセコムWebサインの機能比較
 GMOサイン |  セコムWebサイン | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 有/30⽇間 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 不明 |
| 送信数/月 | 5件 | 不明 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
大手セキュリティ会社のセコムが提供しているセコムWebサインの最大の特徴は、日本では珍しい当事者型の電子契約サービスを提供している点です。
たとえば、A社が秘密鍵を用いて電子署名を行い、公開鍵と契約書をともにB社に送信します。次にB社はA社の公開鍵を使ってA社が電子署名したことと電子書面が改変されていないことを確認した後に、B社は自社の秘密鍵を使って電子署名を行い、署名した電子書面と公開鍵をA社に返信します。
日本で一般的に使われている電子契約サービスでは、立会人型の電子署名が利用されています。当事者型では契約書本人がそれぞれ自身の電子署名を行いますが、立会人型ではサービスを提供する企業の名義で電子署名が行われます。そのため、なりすましリスクを低減させるための仕組みが必要ないメリットがあります。
月額使用料22,000円(税込)~と料金は若干高めであり、自社で認証局に依頼して電子証明書を発行する必要がありますが、セキュリティ性に優れているといえるでしょう。そのため、安全性を重視している方におすすめです。また30日間無料で試すことができるので、自社に合っているか気軽に確かめることが可能です。
Great Sign
引用元:Great Sign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 |
| 送信数/月 | 10件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとGreat Signの機能比較
 GMOサイン |  Great Sign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 |
| 送信数/月 | 5件 | 10件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | |||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | 不明 | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
Great Signは、電子契約サービスに多いオーソドックスな機能を織り込んだサービスです。社内で契約書の承認をまわせるワークフローや書類の一元管理・保管機能を搭載しています。
無料で使えるFreeプランでは契約書の送信件数は10件までですが、有料のlightプランとGreatプランでは無制限に送れます。lightプランは月額8,580円(税込)、Greatプランは月額10,780円(税込)~となっています。
CoffeeSign
引用元:CoffeeSign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 不明 |
| 送信数/月 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとCoffeeSignの機能比較
 GMOサイン |  CoffeeSign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 不明 |
| 送信数/月 | 5件 | 5件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
CoffeeSignとは、使いやすさと作業効率の向上にフォーカスしたSDT株式会社が提供する電子契約サービスです。CoffeeSignという名前の通り、コーヒーを飲みながら契約を終えられるような簡単操作が特徴です。
電子契約が初めての方やハードルが高いと感じる方でも利用しやすいように、使いやすさと洗練されたデザインが高く評価されています。また契約書のテンプレートや編集機能が搭載されていますので、契約作業の効率化も実現できるでしょう。テンプレートは編集・保存できるため、契約書作成にかかる時間を短縮して負担が大幅に軽減させられます。
無料で使えるFreeプランでは、毎月5件までの契約書を送信できます。Tallプランは月額4,400円(税込)で月50件まで送信でき、Grandeプランは月額8,800円(税込)で無制限で利用できます。
eformsign
引用元:eformsign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 有/30日間 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 無制限 |
| 送信数/月 | 100件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | ||
| アドレス帳 | ||
| 下書き保存 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
| 契約更新の通知 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
GMOサインとeformsignの機能比較
 GMOサイン |  eformsign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 有/30日間 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 無制限 |
| 送信数/月 | 5件 | 100件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | ||
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | |||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | |||
| アドレス帳 | |||
| 下書き保存 | |||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | ||
| 契約更新の通知 | |||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 |
eformsignとは、日本フォーシーエス株式会社が提供するクラウド型の電子契約サービスです。WordやExcelなどの文書を手軽に電子文書化できる点が特徴です。また特別な知識がなくても、署名や日付の追加入力を行うだけで、契約書や申請書、稟議書などの電子文書を作成できます。さらに文書ごとにワークフローを設定できるため、複数のメンバーで文書を作成・管理する場合でも使いやすいです。メンバーには代表管理者をトップに設定して、テンプレートの使用者や文書管理者など5種類の権限を付与できます。必要な権限だけを許可できるので、高い機密性を維持しながら文書を管理できます。
無料トライアルは1ヶ月間であり、eformsignのすべての機能を利用できます。最大100件まで文書が送信できるお得なお試しプランとなっています。またPersonalプランは月額2,200円(税込)で文書を月に50件送信でき、超過した場合でも110円(税込)/件で利用できます。Businessプランは月額6,600円(税込)で月に100件送信でき、超過時では77円(税込)/件かかります。1件ずつコストがかかるSmallプランでは、文書を送るごとに77円(税込)かかります。ただし、月に10件までは110円(税込)/件です。毎月1,000件以上送る場合に利用するEnterpriseプランの料金は、企業までお問い合わせください。
DottedSign
引用元:DottedSign
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 不明 |
| 送信数/月 | 3件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 |
| 手書きサイン | 不明 | |
| 印影登録 | 不明 | |
| 認定タイムスタンプ | 不明 | |
| 契約締結証明書 | 不明 | |
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | |
| アクセスコード認証 | 不明 | |
| ⽂書テンプレート登録 | オプション対応 | |
| アドレス帳 | 不明 | |
| 下書き保存 | 不明 | |
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | |
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 |
| 契約更新の通知 | 不明 | |
| フォルダ作成 | 不明 | |
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | |
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
GMOサインとDottedSignの機能比較
 GMOサイン |  DottedSign | ||
|---|---|---|---|
| 無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 |
| 契約内容 | ユーザー数 | 1 | 不明 |
| 送信数/月 | 5件 | 3件 | |
| 署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |
| 手書きサイン | 不明 | ||
| 印影登録 | 不明 | ||
| 認定タイムスタンプ | 不明 | ||
| 契約締結証明書 | 不明 | ||
| 送信機能 | 署名者変更 | 不明 | |
| 署名順設定(順列/並列) | 不明 | ||
| アクセスコード認証 | 不明 | ||
| ⽂書テンプレート登録 | オプション対応 | ||
| アドレス帳 | 不明 | ||
| 下書き保存 | 不明 | ||
| 差込⽂書⼀括送信 | 不明 | ||
| 管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | |
| 契約更新の通知 | 不明 | ||
| フォルダ作成 | 不明 | ||
| ⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | ||
| セキュリティ | ⼆要素認証 | 不明 |
DottedSignとは、台湾を拠点に世界展開している株式会社Kdan Japanが提供する電子契約サービスです。グローバルでの活動実績による安全性が評価され、米国やEU諸国をはじめとした世界各国で利用されています。直感的に操作しやすいシンプルなユーザーインターフェイスが特徴であり、個人から大企業まで幅広く利用しやすいように工夫されています。
優れたセキュリティ機能を誇るクラウドを活用しており、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンからでも利用可能です。そのため、外出先でも手軽にドキュメントにアクセスして契約の進捗状況を確認できます。顧客を訪問して契約を交わす場合でも、タブレットを使ってオンラインでドキュメントに署名できるので、利便性が高いです。IPやデバイス情報をすべて記録するなど厳重なログ記録による優れたセキュリティ環境を実現しているので、安心して利用できます。
フリープランでは、月に3件までの署名が必要な文書を送信できます。プロプランは月額8$/1ユーザー、ビジネスプランでは月額15$/1ユーザーで無制限に利用できます。なお、専任のサポートが付くエンタープライズプランの料金は企業までお問い合わせください。
電子契約サービス人気おすすめランキング

【2024年4月最新版】電子契約サービス比較表
 電子印鑑GMOサイン | 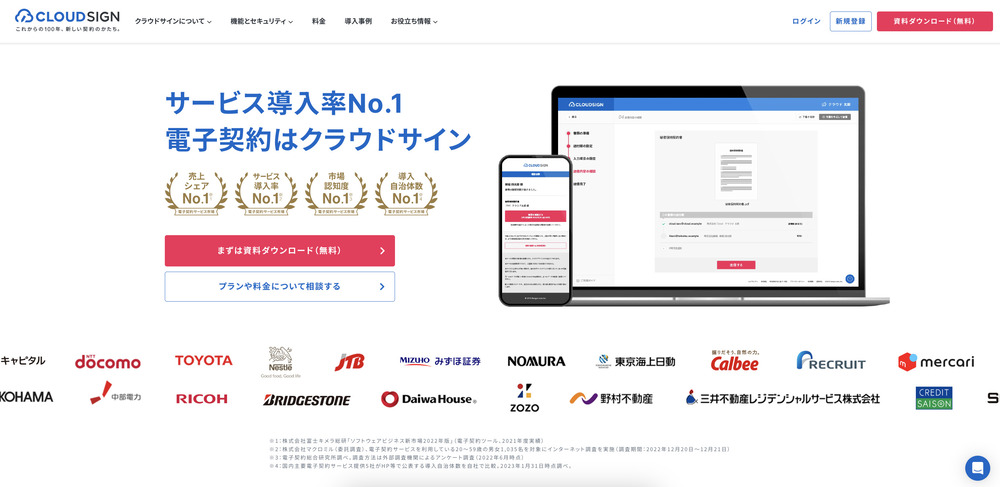 クラウドサイン |  freeeサイン |  ジンジャーサイン | 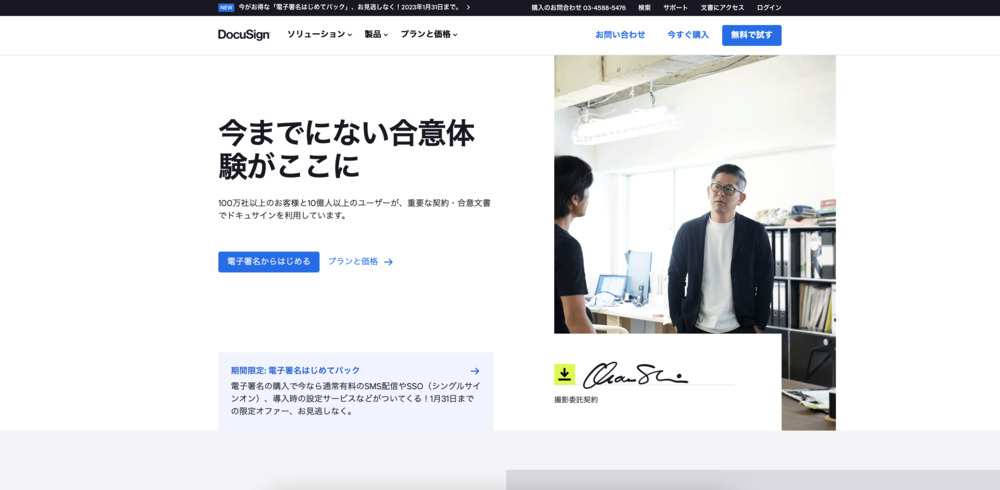 ドキュサイン |  Adobe Acrobat Sign | 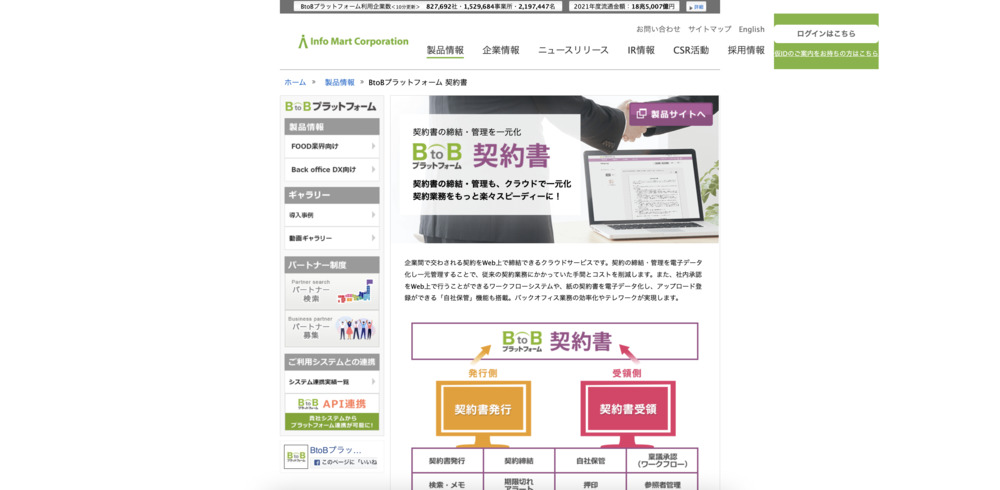 BtoBプラットフォーム 契約書 |  WAN-Sign |  みんなの電子署名 |  paperlogic電子契約 |  マネーフォワード クラウド契約 |  DX-Sign |  かんたん電子契約 for クラウド |  FAST SIGN |  契約大臣 |  クラウドスタンプ | 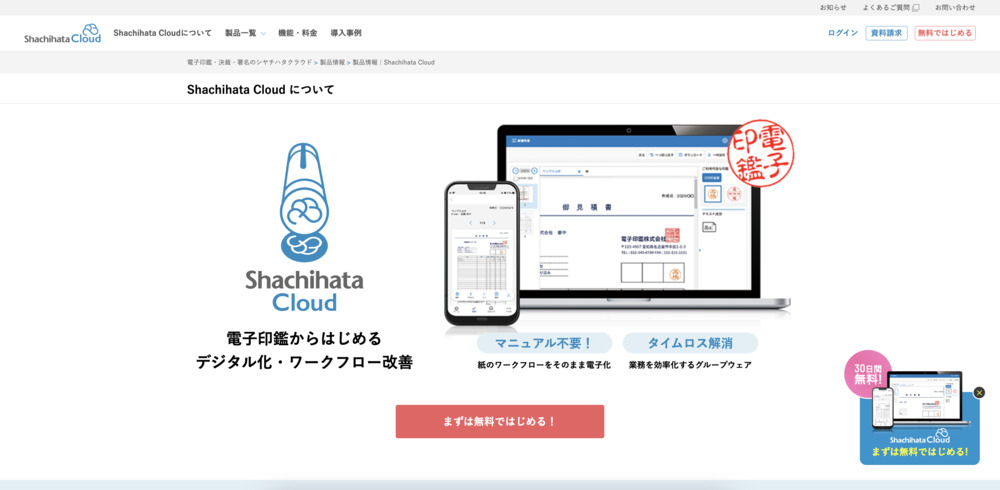 シヤチハタクラウド |  リーテックスデジタル契約 |  ContractS CLM |  CONTRACTHUB@absonne | 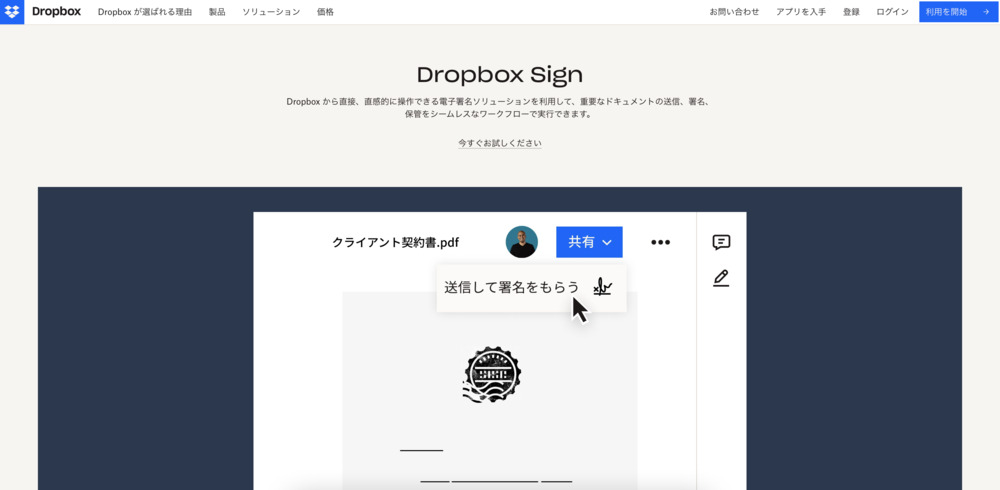 Dropbox Sign |  サインタイム |  セコムWebサイン |  Great Sign |  eformsign |  CoffeeSign |  SkySign |  e-sign | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 無料プラン | 有無 | (署名機能のみ) | 不明 | 不明 | 2023年6月30日をもってサービス終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 送信数/月 | 5件 | 3件 | 月1通まで | 不明 | 5件 | 3件 (保管は累計10件) | 5件 | 10件 | 1件 | 不明 | 最大5通 | 不明 | 月3件まで | 最大25送信 | 最大10送信 | 5件 | 不明 | |||||||||||||
| 有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 110,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 55,000円 | 不明 | 0円 | 不明 | 不明 | 不明 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 月額基本料 | 9,680円 | 30,800円 | 35,760円 | 30,800円 | 4,400円 (1ユーザーあたり) | 2,380円 | 33,000円 | 11,000円 (5,000件ごと/ PDFデータが添付された明細件数のみ課金対象) | 0円 (別途保管料として550円/ 50文書・月/1年間経過した文書) | 22,000円 | 5,478円 | 8,800円 | 11,000円 | 22,000円 (タイムスタンプは別料金) | 9,075円 (年額払い) | 22,000円 | 440円 (1ユーザーあたり) | 55,000円 | 不明 | 不明 | 25ドル | 9,460円 | 22,000円 | 8,580円 | 6,600円 | 8,800円 | 22,000円 | |||
| 送信料(課金体系)/1送信 | 契約印 110円 実印 330円 | 220円 | 220円 | 220円 | 0円 | 55円 | 契約印 110円 実印 330円 | 0円 (保存課金) | 0円 | 0円 (定額料金) | 220円 | 110円 | 500通まで0円 (500通超過後は1通あたり220円) | 0円 | 220円 | 不明 | 0円 | 不明 | 契約印 110円 実印 220円 | 不明 | 不明 | 不明 | 165円 | 100通まで0円 | 110円 | 200円 | ||||
| 送信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 年100通まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 500通 | 100件 | 無制限 | 不明 | 年6,000回まで | 不明 | 不明 | 無制限 | 50通 | 不明 | 無制限 | 100通 | 無制限 | 不明 | |||
| 契約期間 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 不明 | 最低3ヵ月 | 不明 | 不明 | 1年 | 6ヵ月 (その後1ヶ月更新) | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 不明 | 1ヵ月 | 不明 | 不明 | 不明 | |||
| 機能 | ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 10アカウント | 無制限 | 最大50ユーザー | 10アカウント | 無制限 | 無制限 | 50ユーザー | 4名 (4名超過後は1名あたり900円) | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 1ユーザー | 無制限 | 不明 | 不明 | 2〜4名 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 不明 | 不明 | 無制限 | |||
| 契約印タイプ(立会人型) | オプション対応 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実印タイプ(当事者型) | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||
| 認定タイムスタンプ | オプション対応 | 不明 | (3,300円/月100枚まで) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | |||||||||||||||||||||
| 文書管理機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||
| テンプレート機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| API連携 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||
| ワークフロー機能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||
| スマホアプリ | 不明 | (署名できるか不明) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多言語対応(日本語以外) | 英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ミャンマー語/ベトナム語 | 英語/中国語 | 英語/ベトナム語 | 英語/オプション対応 | 英語/中国語(簡体字・繁体字)/オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/韓国語/ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル・ポルトガル)/ロシア語/スペイン語 | 英語/ドイツ語/中国語/韓国語/フランス語/スペイン語/イタリア語/オランダ語など34言語から選択可能 | 不明 | 英語 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 英語 | 英語 | 不明 | 英語 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
| サポート | 電話 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||
| メール・チャット | メールのみ | 不明 | メールのみ | メールのみ | メールのみ | メールのみ | 不明 | オプション対応 | メールのみ | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||
| 導入 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | 不明 | 設定のサポートは無料 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |||
| 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | ||||||||||
| 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | ||||||||
電子契約サービス比較表のダウンロード
電子契約サービスを選ぶ際の注意点

電子契約サービスは便利な反面、利用する場合にはいくつか注意点もあります。また、ひとくちに電子契約サービスといっても、多くの企業がサービスを提供しています。そのため、その中から自社に適したサービスを選ばなければなりません。予算や用途に応じて最適なサービスを選ぶ必要がありますが、まずは以下の項目を満たすサービスであるかを確認してみましょう。
・電子署名法の要件を満たしている
・電子帳簿保存法の要件を満たしている
・費用対効果が見合っているかを考慮する
・契約相手方の負担が少なくて済む
・高いセキュリティレベルをクリアしている
・豊富な導入実績がある
電子署名法の要件を満たしている
ただデータで契約書を作成しても、それは効力を持った有効な契約書といえない場合があります。法律に則って正しく作成された契約書であることの証明が必要です。電子契約を行う際には電子署名法の要件を満たしているか確認しなければなりません。電子署名法の内容は細かく定義されていますが、電子契約締結時には、最低限以下の内容を満たしているか確認することが必要です。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用元:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索
このように、本人による電子署名が付与されていれば、当事者の合意のもとに契約が行われたと証明可能です。
電子帳簿保存法の要件を満たしている
電子契約は電子署名法だけではなく、電子契約書の保管について定めた電子帳簿保存法の要件も満たしていなければなりません。電子帳簿保存法では真実性・可視性の確保が求められています。まず真実性は、以下要件のうち1つ以上を満たす必要があります。
次のいずれかの措置を行う(規8
引用元:Ⅱ 適用要件【基本的事項】|国税庁)
一 タイムスタンプが付された後の授受
二 授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
次に、可視性は以下3つの要件をすべて満たすことが条件です。
引用元:Ⅱ 適用要件【基本的事項】|国税庁
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。)(規3 三イ、
七、8
)
見読可能装置の備付け等(規3 四、8
)
検索機能の確保(規3 五、
七、8
)
このように、データが真実であること、そして参照しやすい状況にあることが、電子帳簿保存法によって求められています。
費用対効果が見合っているかを考慮する
契約するサービスの費用が得られる効果に見合っているかも考慮しましょう。仮に機能面や利便性に優れていても、年間の契約書作成枚数が少ない場合、料金の高いサービスでは、コストパフォーマンスが高いとはいえません。自社がどれぐらいの頻度で電子契約を利用するのか、多すぎる場合は効率的にデータを管理できるのかなど、予算と状況に応じて適切なサービスを選択することが必要です。
契約相手方の負担が少なくて済む
紙媒体の契約書は作成したら相手方に送付する必要があり、手間や時間がかかってしまいます。電子化された契約書であれば、相手もPCやスマホ上で確認できるため手間が省けます。しかし、電子契約サービスの中には、相手方も同じサービスに登録していなければ、確認できないものもあります。これでは相手方の負担にもなるため、なるべく相手がサービスに契約していなくても契約締結や確認ができるものを選択しましょう。大手の電子契約サービスは、相手側が会員登録していなくても利用可能なものが多いため、優先的に選ぶことをおすすめします。
高いセキュリティレベルをクリアしている
データとして扱う以上、外部からの攻撃や誤った操作による情報漏洩などは特に気をつけなければなりません。データはサービスを利用している以上、インターネット上に残り続けます。そのため、高いセキュリティ性を持ったサービスを利用しなければ、紙の契約書よりも管理リスクの高いものとなってしまいます。契約書の閲覧権限を設定可能か、契約書と同時に電子証明書も提出できるかなど、高いセキュリティレベルを有しているかを必ず確認しましょう。
豊富な導入実績がある
大手企業が導入していたり、導入企業数が多かったりする電子契約サービスは、それだけセキュリティ性や利便性が優れているといえます。どのサービスを導入すべきか悩んでいる場合は、豊富な導入実績を持つサービスを調べたうえで、問題がなければ、優先的にそちらを選択するとよいでしょう。ただし、導入コストは企業の状況次第であるため、適切なコストで利用できるかは自社で慎重に検討しましょう。
電子契約のメリット8つ


印紙税がかからない
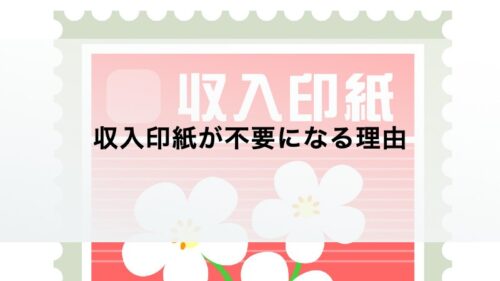
電子契約では、印紙税がかからない点が最大のメリットといえます。紙の契約書では、基本的に印紙税の課税対象になります。しかし、電子契約では相手方に渡すのは電磁的記録であるデータです。
契約書にかかる印紙税は、企業の場合では契約金額や回数によって大きな金額になりえますので、このコストを削減できる点は大きなメリットといえるでしょう。
さまざまな経費を削減できる
電子契約では契約書はデータで保管しますので、必要なものはサーバーなどのデータ容量だけになります。そのため紙媒体で契約する場合と比べて、用紙代やファイル代などを節約できます。インク代やプリンター代もカットできるので、かなりの費用を削減できます。
また、契約書の締結にかかる時間のカットにも役立ちます。相手方が電子契約に慣れているならば、移動費や契約に要していた時間を削減できますので、労働時間や人件費を無駄ななく使えるようになります。
さらに、ハンコも必要もありません。電子契約では電子ハンコなどによって、契約書の正当性を担保しますので、印鑑や朱肉も必要なくなります。この点でも経費削減にもつながるでしょう。
契約締結のリードタイムを大幅に短縮できる
紙での契約では上司や取引先などに内容を確認してもらうため、足を運んだり郵送で書類を送ったりするなど契約締結までにかなりの時間や手間がかかっていました。しかし、電子契約ならばメールなどでデータを送信して承認もらうだけですので、スムーズに契約を完了できます。
また、昨今ではオンライン会議などができるツールも多く使われるようになったため、併用してオンラインで契約を進めれば、リモートでの契約も可能です。契約書類もそのままWeb上で保管できますので、契約業務を一貫してパソコン一つで完結できます。業務を進める上でミスが少なくなり、大幅な時間短縮と業務効率化を実現できるでしょう。
業務を効率化できる
電子契約を採用すれば、Webで書類を送るだけで確認してもらえます。そのため、紙の契約書でかかっていた時間や手間を大幅にカットできます。
また、書類の保管や確認作業でも効率化が図れます。紙の書類では、契約書を種別や年などの項目ごとに分けて保管する必要がありました。そのため、必要なときに探すにも時間がかかっていました。その点電子ファイルならば、Webに保存するためスペースや分ける作業が必要ありません。検索機能を使えば、過去の記録を簡単に検索できます。
さらに、契約の締結までにかかっていた時間や手間を削減できるので、その分を別の仕事に割けるようになって、業務効率が良くなります。残業時間の短縮やライフワークバランスが向上につながるので、業務の生産性向上も期待できるでしょう。
文書の保管・保存が簡単になる
電子契約サービスを利用すれば、契約書は種類ごとにフォルダ分けされて保存されます。そのため人的ミスを少なくでき、過去の契約書を探す作業もスムーズに行えます。
コンプライアンス(法令遵守)を強化できる
電子契約サービスでは提供企業がコンプライアンスを遵守しているため、サービスを導入すれば法令遵守の強化につながります。紙の契約管理と比べて、人的ミスがかなり少なくなりますので業務が管理しやすくなるでしょう。
押印のために出社する必要がなくなる
電子契約では電子ハンコが使用できるため、社内の書類決裁や社印が必要な書類の作成などの業務でも出社して書類を作成する必要がなくなります。電子契約サービスでは基本的に契約に必要なフォーマットや電子印鑑、電子署名が登録・作成できるため、パソコンさえあればどこでも書類を作成できるようになります。
環境保護につながる
紙に印刷する必要性がなくなるため、紙の使用量を減らせます。また、消耗品の使用頻度を少なくするなど契約書の作成に必要なものが減らせるため、ごみの排出量を減らして環境保護につながるでしょう。
電子契約のデメリット7つ

導入や運用にコストがかかる
電子契約を導入するには、電子契約サービスを提供している会社と契約する必要があります。この契約に関するコストは、紙契約ではなかった必要費用といえます。
またリモート業務を行う場合には、社外に持ち出せるパソコンや個人所有のパソコンにセキュリティ対策など運用面でコストがかかる可能性もあります。
社内調整が必要
新しいサービスやソフトを業務に導入するには、パソコンを使用して業務を行っている社員や管理者である上司などに対して社内における調整が必要です。そのためには、事前の社内での調査や使用感を確かめるためのテストなどの期間を設ける方法など考えられます。それらの所感から、どのような電子契約サービスが自社に合っているのか確かめていると良いでしょう。
さらに電子契約で締結した契約書は、法人税によって7年間の保管義務が生じます。データで7年間保存しなければならない点も、社内調整が必要な部分となるでしょう。
取引先の理解が必要
電子契約サービスでは、社内の賛同が得られても、社外の理解が得られないとスムーズに運用できません。そのため導入時には、事前に契約方法の変更を取引先に通告する必要があります。
取引先によっては、パソコン作業が苦手だったりそもそもあまり行わなかったりする事業者や個人も存在します。そういった方々に対して真摯に説明するとともに、電子契約に不慣れな取引先にはサポートすべきケースもあるかもしれません。
電子契約を利用できない契約がある
2021年9月に施行されたデジタル改革関連法案では、多くの契約が電子契約可能になりました。しかし、以下の契約ではまだ紙での契約が必要です。
・事業用定期借地契約
・企業担保権の設定または変更を目的とする契約
・任意後見契約書
・特定商取引(訪問販売など)の契約
これらの契約は現時点(2024年4月時点)ではまだ電子化できませんが、今後の動向によっては電子契約できるようになる可能性もあります。そのため、法改正などには注意が必要です。
サイバー攻撃の被害に遭う可能性がある
パソコンがインターネットにつながっている企業では、どんなシステムやサービスを使っていてもサイバー攻撃を受ける可能性があります。そのため電子契約サービスの導入時には、書類の複合化が難しい暗号化を採用していることやクラッキングされにくいシステム・サービスを使っていることなどを調べた上で決めなければなりません。
また、自社で社員それぞれにパソコンを整備する場合には、JSBなどの外部記録媒体を認識されないプログラムを導入すると良いでしょう。個人用パソコンを使う作業では、個人用パソコンからファイルがアップロードされた場合にウイルスに感染していないかをチェックするなどの機能もあると望ましいです。
契約締結日を更新できない
多くの電子契約サービスでは、電子署名やタイムスタンプによって法的に契約書として問題ない書類として取り扱えます。
そのため、契約後に契約日時を更新する場合には、前の契約書を破棄して新たに契約書を結ぶ必要性があります。
自社に合った電子契約サービスを選ぶのが難しい
多くの会社が電子契約サービスを展開しているため、自社に合ったサービスを選びにくいという点のデメリットといえるでしょう。ほとんどのサービスでは電子署名やタイムスタンプだけでなく、本人確認の強化や契約締結した書類の暗号化、契約書種類ごとのフォルダ保存といった基本的な機能が備わっています。
そのため、主に操作性や料金、作成する契約書にあった電子契約サービスであるかがチェックポイントになります。たとえば契約相手に個人が多い企業では、個人に対して電子契約がしやすいサービスを選択すべきでしょう。また法人同士の契約が多い企業では、提供される契約書のテンプレートが自社で登録できるのか、テンプレートが自社に合っているのかといった部分を事前に確認しておく必要があります。
このような面を確認するためには、無料で使える電子契約サービスを試験的に導入して使用感を確かめると良いでしょう。
電子契約にまつわるよくある質問と回答
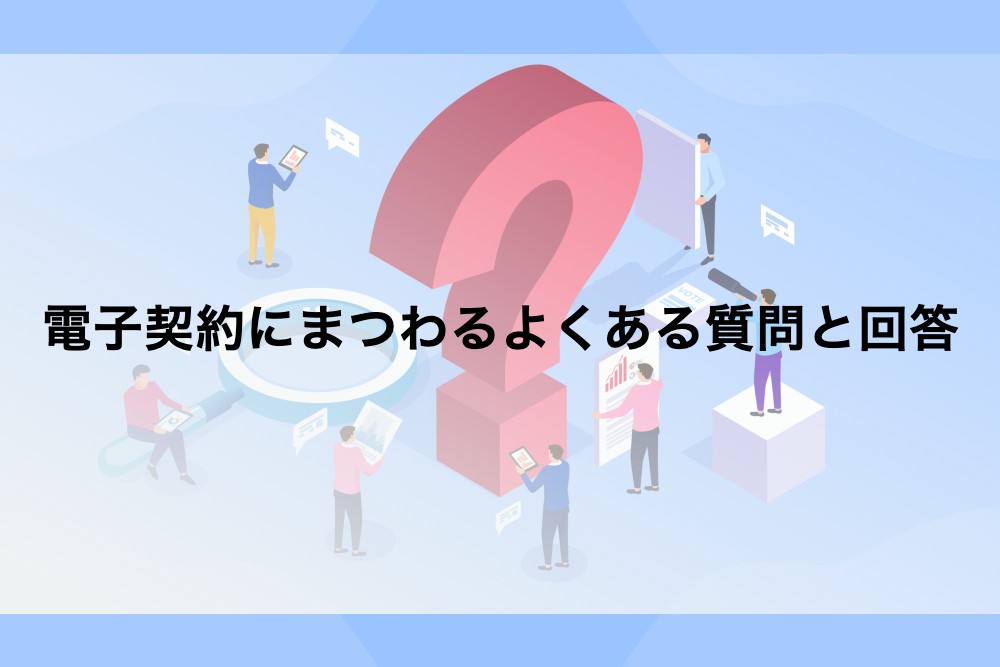
電子契約でよくある質問をまとめました。これまで紙媒体で契約書を作成してきた方にとって、便利そうな反面データでの管理に不安を感じることも多いでしょう。電子契約サービスをこれから利用するにあたっては、まずこちらの内容を確認してみてください。
電子契約とは?
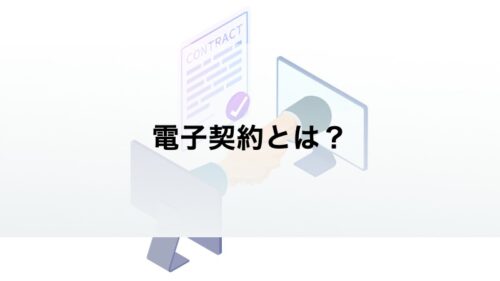
社会で活動するにあたっては、どこかから仕事を受ける、もしくはどこかに仕事を依頼することも多くなっています。その際には、後のトラブルを避けるために契約書を作成することが多いでしょう。契約書には仕事内容や納期、報酬金額などが記載されており、双方がその内容を確認して同意したとみなす大切な書類です。従来の契約書であれば、紙媒体で作成されて、当事者が確認のうえ捺印などを行うことで同意したとみなされていました。しかし、メールやチャットなどインターネットを活用したツールが普及している現代では、契約書もデータ化する流れが主流となっています。契約を電子上で交わすことを電子契約と呼び、PDFなどのファイル形式でデータ化された契約書を作成して保管する形式になります。紙媒体で契約書を作成する企業もまだまだ多いですが、電子契約だからこそ得られるメリットもあります。そのため、セキュリティ面に最大の配慮をしたうえで導入を進める企業も増加中です。
なぜタイムスタンプは必要なの?
紙の書類は内容を書き換えられますが、これは電子データでも同じです。契約書を交わした後に内容の一部が改ざんされる問題は、紙でもデータでも起こりうる可能性があります。特に原本が電子上にある電子契約書の場合は、紙よりも簡単に改ざんができてしまいます。この問題を解消するために、電子契約ではタイムスタンプと呼ばれる仕組みが導入されています。タイムスタンプとは、対象のデータが存在していたことを証明する記録です。これがあることで、電子契約が締結されたのはいつか、内容に変更があった場合、その変更日時はいつかが正確に記録されます。この仕組みが導入されることで、契約後の不当な改ざんを防止できるのです。
電子契約のやり方とは?
データで作成された契約書をもとに、当事者が確認・同意すれば契約締結となりますが、真正に成立したと証明するためには電子署名法の要件を満たすことが必要です。法的要件を満たしている電子契約サービスを活用して契約書を作成することで、真正に電子契約が成立します。そのため、電子契約書を作成する側は電子契約サービスに登録する必要があります。
電子契約に法的効力はある?
契約は原則としてどのような形式であっても成立するため、電子契約であっても有効な契約となります。しかし、訴訟において証拠とするためには、電子署名などの要件を満たすことが必要です。電子署名法の要件を満たした電子契約であれば、真正に成立した契約であると推定されます。逆に、要件を満たしていないものは、訴訟における証拠とはできないため、電子契約を交わす際は要件を満たした契約書の作成が必要不可欠です。
電子契約を導入するメリットとは?

紙媒体で契約書を作成する場合、紙のコストがかかることはもちろん、作成にあたっての事務労力もかかります。しかし、電子契約であればテンプレートを用いて、必要事項を打ち込むだけで、印刷不要なデータとして取り扱えるためコスト削減や業務効率化が図れます。また、作成した契約書を管理する場所もPCやサービス上になるため管理も容易となり、紙での管理と比べると紛失のリスクも大幅に削減できるでしょう。
電子契約の導入は、印紙税の節税にもつながります。紙媒体の契約書は、金額に応じた収入印紙を貼り付けて印紙税を納税しなければなりません。しかし電子契約書の場合は収入印紙を貼り付ける必要がなく、印紙税も非課税となります。契約書を多く作成する場合は、電子契約を導入した方が節税につながります。
電子契約にはどんなデメリットがある?
電子契約は便利である反面、取引相手にそのサービスの利用を強制させてしまう場合もあります。大手の電子契約サービスであれば、相手方の会員登録は不要な場合が多いですが、相手にもデータを確認してもらう必要があるなど、一定の協力は求めなければなりません。取引先も自社の都合があるため、コストや労力の観点で導入が難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、こちらとしても電子契約の活用が難しいことになります。電子契約自体は普及してきているものの、まだまだ紙媒体でのやり取りを行う企業が多いのも事実です。
電子契約におけるリスクとは?
電子契約は便利である反面、情報漏洩の恐れがあります。また、要件を満たしているか確認することも必要です。インターネット上でやり取りする以上、外部からの攻撃やセキュリティリスクは常に存在します。このリスクを考慮したうえで、安全に活用できるよう、導入するサービスや社内での利用方法はしっかりと検討しましょう。
電子契約で印紙税がかからないのはなぜ?
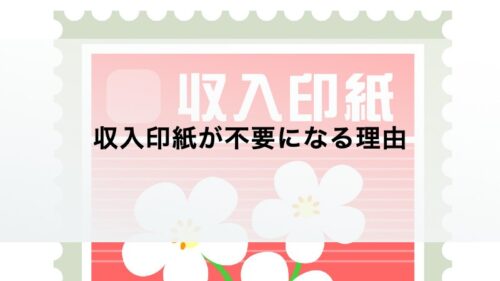
電子契約で印紙税が非課税となるのは、対象となる課税文書は用紙に記載されているものと定義されているためです。電子契約サービスで作成された電子契約書については、課税文書に該当しないと国税庁も見解を示しています。
印紙税法上の「契約書」とは、印紙税法別表第一の「課税物件表の適用に関する通則」の5において、「契約の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。」と規定されている。
引用元:(別紙)|福岡国税局
また、印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、印紙税法基本通達第44条により「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、当該交付の時であるとされている。
上記規定に鑑みれば、本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものである。しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。
今後の法改正で課税対象に変更される可能性もありますが、節税のためにも積極的に活用することをおすすめします。
電子契約を無料で使う方法は?
電子契約サービスのほとんどは、月額・年間料金を払っての利用になります。しかし、一定期間であれば無料で利用可能なサービスもあるため、初めて電子契約を導入する方は、まず使ってみることをおすすめします。
どの電子契約サービスを選べばよい?

電子契約サービスの選択肢は多岐にわたります。どれを選ぶべきか悩む場合は、導入実績やコストの観点から候補を絞り込んでみましょう。導入実績が多いサービスは、利便性が高く、セキュリティ性も保証されていると考えてよいでしょう。ランニングコストのかかるサービスでもあるため、自社の状況に応じて見合ったサービスをその中から探します。電子契約サービスの導入は節税や業務効率化など多くのメリットがあるため、契約書を多く作成するのであれば費用対効果も高くなるはずです。これらメリットを加味して最適なサービスを選択しましょう。
電子契約サービスを導入して業務効率化を図ろう!
電子契約サービスを導入することによって、面倒な契約業務をスピーディーかつ負担なく行うことができるようになります。また、印刷代や印紙代などの大幅なコスト削減につながります。
ただ、電子契約サービスを導入したいと思っても、「種類が多すぎてどれを選べばいいのかわからない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
引用元:GMOサイン
GMOサインは、導入企業数350万社(※2024年4月時点)以上の実績を持ち、多種多様な企業が利用している国内最大級の電子契約サービスです。
“期間の定めなし”で使い続けることができる無料プラン(お試しフリープラン)が用意されているので、自社の目的に合ったツールかどうか気軽に試すことが可能です。利用しても利用しなくても、料金が発生することはありません。
月額9,680円(税込)の有料プラン(契約印&実印プラン)なら、送信数やユーザー数が無制限となります。本人性が高い実印タイプでの署名も利用可能です。さらに、閲覧制限や操作ログ管理などの便利な機能も利用できるようになります。
パソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレットでいつでもどこでも時間や場所にとらわれず柔軟に契約を結ぶことができるのも嬉しいポイントです。GMOサインを活用すればハンコを押すためだけにわざわざ出社をする必要がなくなります。
充実した機能を搭載、高度なセキュリティで安心・安全、利用期間の定めなく無料で使える『GMOサイン』をぜひ一度試してみてください。