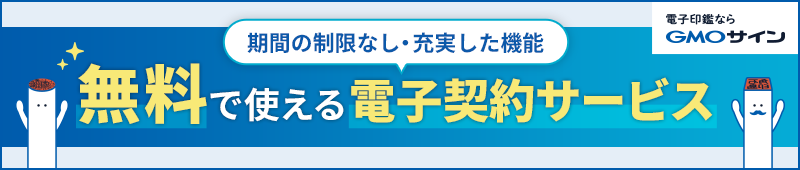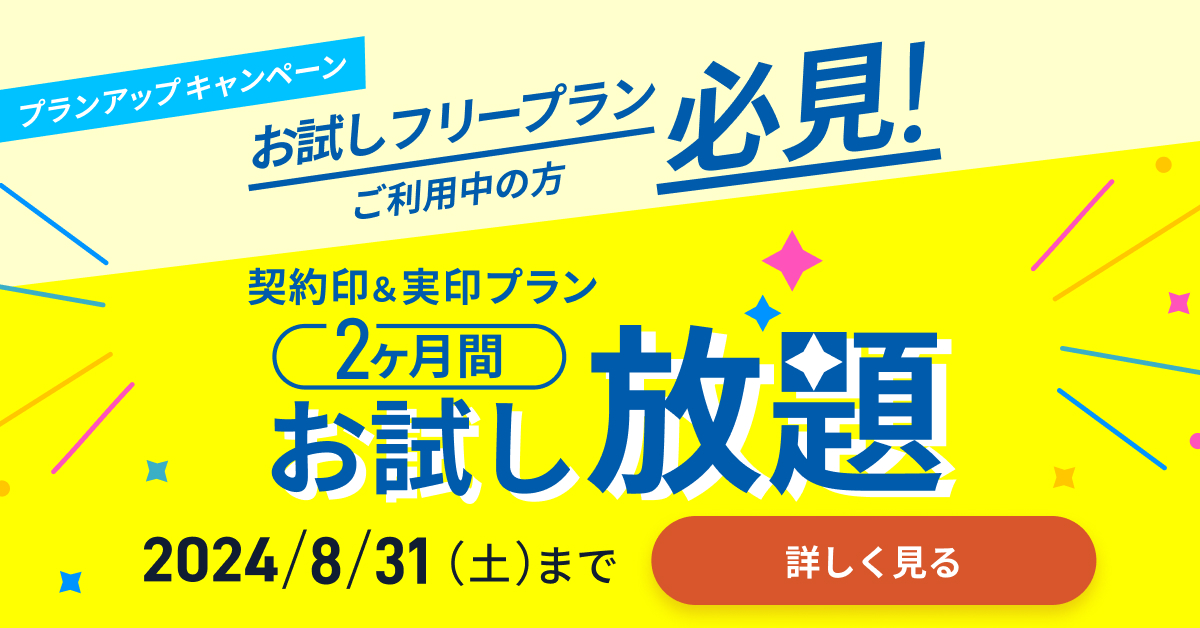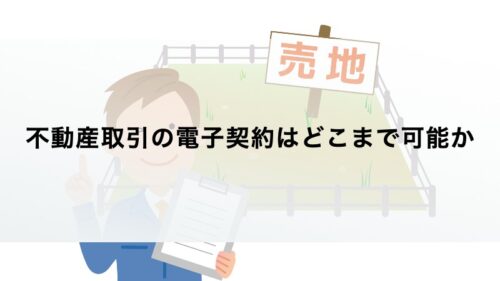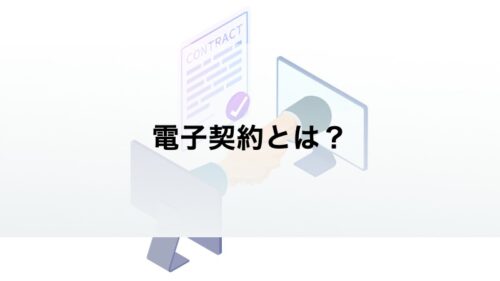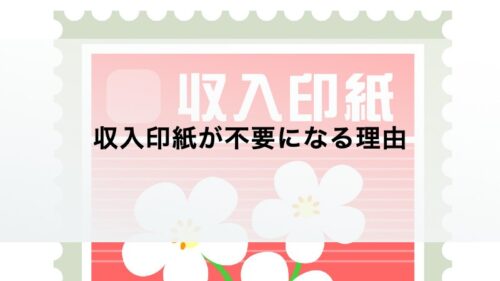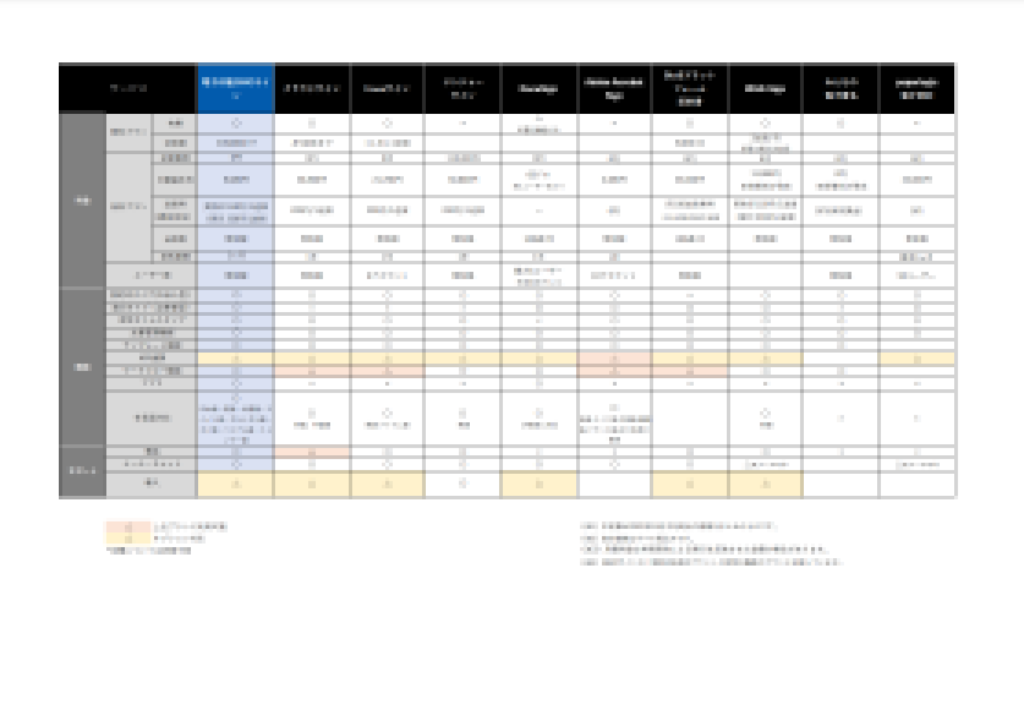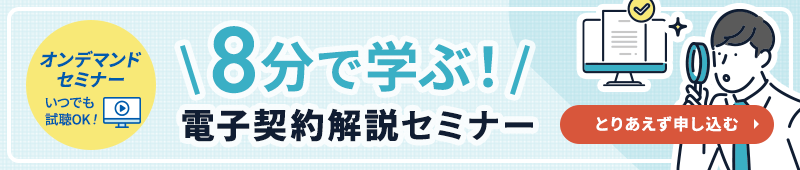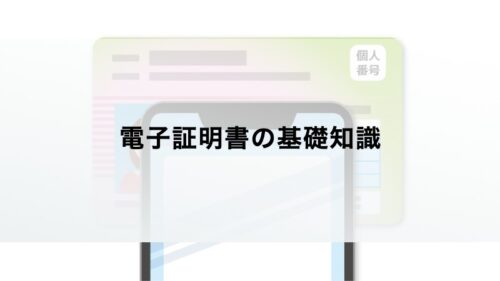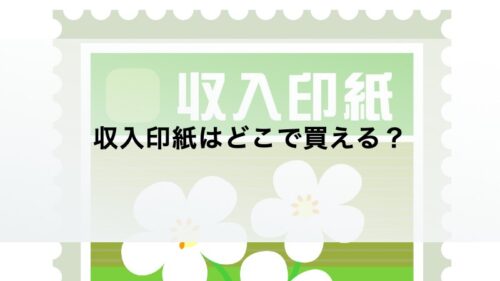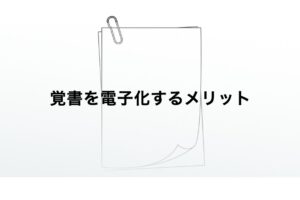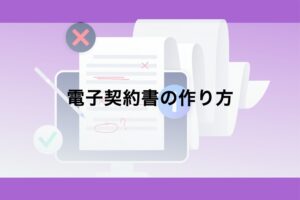書面での契約書から電子契約へ移行する企業が増えています。2022年5月には不動産取引に関する売買契約書の電子化が解禁されるなど、身近な商取引にも影響が及んでいるのが現状です。これまで関わってこなかった人も、電子契約に接する機会は増えるでしょう。
あわせて読みたい
不動産取引における電子契約の導入で何が変わる?メリットや注意点を徹底解説!
2020年から始まった新型コロナウイルス感染症による外出規制に加え、2022年5月の不動産の電子契約解禁の流れによって、不動産契約の電子化は徐々に浸透してきています。...
今回は、電子契約の基本とともに、メリットとデメリットも解説します。電子契約を導入するための注意点も説明しますので、最後までお読みください。
目次
電子契約とは
電子契約とは、電子文書に電子署名等を付与することで成立する行為です。
文書を電子ファイル化してインターネット上でやりとりし、改ざん防止のために電子署名を付与するなどの対策がとられています。このほか、契約書の本人確認のために電子証明書を付与したり、改ざん防止のためにタイムスタンプ機能を利用したりする対策も有効です。
書面での契約から電子契約に切り替えることにより、業務効率化やコスト削減などのメリットが期待されています。
あわせて読みたい
電子契約とは?基礎知識や仕組みをわかりやすく解説!導入するメリットや注意点も紹介
働き方改革やペーパーレス化の一環として、電子契約を取り入れる企業が増えています。電子契約によってインターネット上で契約を締結することが可能になり、紙の契約書...
電子契約のメリット
電子契約はインターネット上でやりとりを行うため、対面する手間やコストが省けるほかに、普段行っている業務も効率化されます。ほかにも、書庫スペースの削減、コンプライアンス(法令遵守)の面でも効果的です。特に、普段の業務フローを一から見直せるのは、大きな利点といえるでしょう。
ここでは4点のメリットについて、順に解説していきます。
業務効率化
契約行為は企業活動の大切な事務です。これが省力化されることで、これまで必要だった契約事務の労力が削減され、事務経費の削減にもつながります。
また、これまで人員の往復や郵送などで時間を要していた契約にかかる時間が短縮されるので、契約締結までのリードタイムの大幅な短縮が可能です。
書面で作成しなくて良いので、契約書の作成が容易で時間がかかりません。さらに、契約承認のために出社する必要もないので、リモートワークの継続が容易になります。
コスト削減
電子契約によるコスト削減で一番効果があるのは、印紙税の削減です。書面との契約とは異なり、電子契約は印紙税が不要ですので、収入印紙を用意する必要がありません。
あわせて読みたい
なぜ電子契約には印紙税がかからないのか?収入印紙が不要になる理由を解説
電子契約を利用すると、印紙税が不要になるのでおすすめです。しかし、これまで必要だった印紙税がなぜ不要になるのか疑問に感じる方も多いでしょう。 そこで本記事では...
このほかにも、契約書作成にかかる人件費や郵送費、保管費用なども削減できます。手間のかかる作業負担が減るだけではなく、コストが軽減されるのは大きなメリットです。
書庫スペースの削減
電子契約では、大量の書面書類が電子化されるので、保管のための書庫スペースが削減され、書類管理も効率化します。不動産業界など紙の量が相当多い業界では、大きな効果を発揮するでしょう。
また、電子ファイルを保管する装置は必要ですが、大きな容量は不要なうえ検索もできることから、これまでかかっていた業務時間も一気に短縮されます。
コンプライアンスの強化
電子契約では契約状況が可視化されるので、上司や関係部署が進捗状況を確認でき、契約更新の有無や内容のチェックも容易に行えます。従来は紙ベースだったものをシステムで瞬時に確認できるのは、便利であるとともにコンプライアンスの強化にもつながります。
電子契約に関する法律
前章で触れたように、電子契約は従来の書面と比較して多くのメリットがあります。さらに、国のDX推進を受けて、電子契約を導入する企業が増えています。印刷が不要で印紙代がかからない、押印も不要というメリットがありますが、それぞれ法令上の根拠を整理しておきましょう。
電子契約に関する法律について解説していきます。
民法
民法522条の2項では次のように定められています。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
したがって、電子的な取引も有効に成立します。
印紙税法
印紙税法は、一定金額以上の取引に関わる契約書や領収書に対し、印紙税を課すことを定めた法律です。
第162回(平成17年3月15日)の国会答弁で、電子契約には印紙税がかからないことについて明言されています。
文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
引用元:第162回国会(常会)答弁書|衆議院
e-文書法
e-文書法とは、次の2つの法律の総称です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
商法や税法などで保存が義務付けられている文書について、電子保存が認められています。
電子署名法
電子署名法は、電子署名に法的根拠を与えた法律です。
第3条で次のように定められています。
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用元:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索
これにより、電子署名された文書の有効性が担保されています。
民事訴訟法
民事訴訟法の第228条では、文書の成立が真正である条件について、次のように定められています。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
引用元:民事訴訟法 | e-Gov法令検索
ここで言う署名又は押印は、電子契約においては電子署名を指すとされています。
IT書面一括法
IT書面一括法とは、相手が承諾したことを条件に、書面の代わりに電子メールなどの情報通信技術方法による交付を認めた法律です。
正式名称は、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」といいます。顧客保護を目的として、事業者に電子メールなどを使った書面の交付や手続きに関するルールを定めている法律です。
IT書面一括法という独立した法律があるわけではなく、金融庁や総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省がそれぞれ定めている法令をまとめたものを指しています。
電子帳簿保存法
電子契約を導入した場合は、電子帳簿保存法に従って電子契約書を保存しなければなりません。
帳簿や領収書・請求書・注文書・契約書など電子取引に関する書類を電子データで保存することが認められています。保存方法について、電子データで書類を保存することを許可される要件や保存の方法、タイムスタンプの付与、書類の要件などが定められているのが特徴です。
電子契約のデメリット
電子契約には、業務の効率化をはじめとした、多くのメリットがあります。一方で、電子契約の普及が一気に進んでいないのも事実です。
ここでは、電子契約で懸念されるデメリットについて、3点を挙げて解説します。
取引先の対応が必要
電子契約がいくら便利だといっても、契約の相手先が対応していなければ利用できません。中小企業では、紙の契約書しか取り扱っていないケースもあります。この場合、自社に合わせて電子契約を行うには、契約相手先に電子契約を行う体制を整えてもらうことが必要です。
場合によっては、電子契約に対応した作業手順やシステムの紹介を行わなければならないかもしれません。契約相手がどうしても対応できない場合には、相手に合わせて従来通り書面で契約し、書面の管理も行わなければならないでしょう。
社内への説得が必要
電子契約サービスを導入するためには、社内の調整が必要です。これまで行っていた業務フローを変更しなければならないので、時間を要する場合があります。業務関係部署や操作担当者へ説明を行い、理解を得ることが大切です。社内で書面での契約から電子契約への移行が認められた場合は、操作説明が必要となるのでコール窓口の設置も必要です。
そもそもITに対する抵抗感がある場合は、ていねいに進める必要があるので、社内調整と教育は慎重に行いましょう。
サイバー攻撃のリスクが顕在化
電子契約を行う際には、外部との契約を管理するサーバーが必要です。外部からアクセスできるサーバーを自社で設置する場合は、サイバー攻撃のリスクに備えなければなりません。
信頼できる第三者のサービスを利用する場合には、自前でサーバーを立てないまでも、万全のセキュリティ対策を講ずる必要があります。システム導入も含めて専門家の支援が必要となるでしょう。
電子帳簿保存法への対応
電子契約を行うには、電子帳簿保存法への対応が必要です。
請求書や領収書だけでなく、取引にかかる書類も保存の対象になります。
電子帳簿保存法へ対応するには、国税庁が法律で定める次の要件を満たす必要があるので押さえておきましょう。
- 電子データの保存場所と保存期間
- 真実性の要件
- 検索機能
これらの要件に的確に対応するには、システム導入業者だけではなく、会計事務所との打ち合わせも欠かせません。
【参考】電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
電子帳簿保存法の適用直後は、これらの基準をすべて満たしているかについて税務調査が行われることも予想されます。税務調査で指摘を受けることのないよう、適切に対応しましょう。
電子契約に対応していない契約への対応
法整備が進んで契約書の大半が電子化されましたが、電子化が認められていない契約もあります。ほとんどの契約は電子契約で対応できますが、一部電子化に対応していない契約は書面で契約しなければなりません。そもそも電子契約に対応していないものや、契約相手によっては対応できないものがあるので、電子契約と紙の契約が混在することになります。
しばらくは、契約管理は書面と電子の両方の方法で対応することになるでしょう。
電子契約を導入する際の注意点
これまでみてきたように、電子契約には確かにデメリットはあるものの、業務を効率化できるメリットの方が大きいので、遅かれ早かれ導入を進めていくべきものと判断されます。
今後、電子契約を導入する際には次の3点に注意して準備を進めましょう。
社内関係者への説明
社内の法務や契約を担当する部署では、電子契約に関する経験に乏しく、導入を躊躇することもあります。これらの部門には、法律的な根拠や手続きの有効性などを入念に説明して理解を得ておくことが必要です。一度理解を得られれば、組織の業務効率化につながるため、その後は積極的に推進してくれるかもしれません。
また、一般の社員にも教育を徹底する必要があります。今まで困っていなかったと感じる社員にメリットと効果を示すことができれば、効果的な教育が可能です。誰ひとり置き去りにすることなく、全体のレベルを合わせておかないと、予想外の問題が発生して効果が発揮できないことがあります。関係者や一般社員への説明をていねいに行っていきましょう。
業務フローの見直し
電子契約を導入するかしないかに関わらず、業務フローの見直しは必要です。業務効率化のためにできることがあれば常に改善していきましょう。
紙による契約業務は、時間がかかることが一番の問題です。電子契約を導入することにより、業務が大幅に効率化されるはずです。作業時間を節約するためにも、紙ベースでの事前送付、オンライン説明、メールでのやりとりなど、業務を根本から見直すことになるでしょう。電子契約を導入するに際し、改善したい部分を明確にすれば、見直す範囲も容易に把握できます。
現在は法律上、電子化できない契約もありますが、今後は要件緩和が予想されますので、早いうちに見直しを進めておくとよいでしょう。
契約先へ周知
電子契約を円滑に導入するには、契約先への周知が欠かせません。未導入の契約先には、そもそも電子契約がどういうものか、信用性と信頼性をどう確保するのか、手続きがどう変わるのかといった基本を説明したうえで、多くのメリットがあることも含めて理解を得る必要があります。
契約先の業務内容が大きく変わる可能性もあるので、余裕を持ってしっかりと周知を行いましょう。
理解が得られない場合は、書面での契約が残ってしまい、電子契約と平行して契約事務を行わなければならなくなるため注意が必要です。
まとめ
書面での契約から電子契約へと移行が進んでいます。まだ電子契約を導入していない企業でも、以下のようなメリットがあることを理解して、今から電子契約に移行する準備に取り組んではいかがでしょうか。
・業務効率化
・コスト削減
・書庫スペースの削減
・コンプライアンスの強化
電子契約を進めるためには、社内の関係者への説明や業務フローの見直しに加え、契約先への周知も必要となります。電子契約が必要とされる案件は今後も増えていくことが予想されますので、今から検討を始めておきましょう。
この記事が電子契約を検討している企業のお役に立てば幸いです。